

@kR_Đi˝ń´ńśńśáj\OdÎiŢǧ÷äs˝őj
@ \OdÎÍÉhĚÎĺH äsłi˘ĚäŤŕĆjĚěiĹAĄ´säiWCöjĚćĆ`Śé

kR_Đ\OdÎidvüpiAqăăú imZN 1298NAÔźâAł ń450Cm)
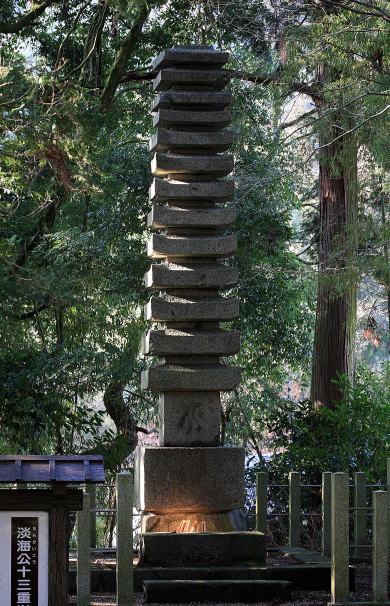 |
 |
|
| gAÖŕÉŕEl§Ěíqđň¤¤čˇéi^[NFóśj | ||
 |
||
| \OdÎÍWCöiĄ´säjĚćĆ`Śé | gAÖŕÉŕEl§Ěíqđň¤¤čˇéiE[F˘ź¸j |
 @
@
îbńĘÉuimZNi1298jčúOAŠiZŞčOvuĺHäsłvĚÁŞ é
íÉĚl\ŞčÉöŢZŞčOƢ¤˘íÉMÂĚOŞA˘§ľ˝BäsłÍAÉhÎĺHĚęl
 |
 |
|
| gAÖŕÉŕEl§Ěíqđň¤¤čˇéiANFsóŹAj | ||
 |
||
| gAÖŕÉŕEl§Ěíqđň¤¤čˇéiL[NF˘íÉj | wĘŠçŠéĆA\OdÎÍŠČčjšľÄ˘é |

ewĚŽŞÍA ÉędĚŘ^đÂéBŹ˝ÍAqăăúĚlŽđć`ŚÄ˘é
ŢÇđĘoXukR_ĐoXâvşÔAoXâŠç¤ĚKiđşčÄkR_ĐÉsšĚKiđ~čŤÁ˝É\OdÎÖĚűüÄધÁĢé
@kR_ĐźĺÎ_ĚăÉ éqăúĚíčÓ§

kR_ĐíčÓΧiqăú śiON 1266NAÔźâAł 150Cm 79Cm sŤ 37Cm)
 |
 |
|
| ĄŮ˝ÔŔĚăÉĄŮ@ŔAD`őwđÂčAEč {łŘóEśč InóĚíčÓđęÎŤčoˇ | ||
őwĘśEÉuśiONi1266jŞŞúň˘§vuĺŠiłĺHĄä´vĚÁŞ é

ÂĘŕiM\ji]ËăAÔźâAł 64.5Cm)
íčÓΧćčkR_ФĚÎ_ăÉ é
![]() @kR_ĐźűĚΧĆÂč@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@kR_ĐźűĚΧĆÂč@@@@@@@@@@@@@@@@@@![]() @@@@@@@
@@@@@@@![]() @ΧĆÎ-ÚI
@ΧĆÎ-ÚI

ąąÍA ˝őyĚźĺŐnA˘ć螥łNÜĹļżüčđÖś˝EnĹ Á˝
p§ĘßÉćčyÍkR_ĐĆČčulÖ§vŕđŠę˝
| wIN |
ßSu÷äwvćčAŢÇđĘoX kR_ĐsŤćÔAukR_ĐoXâvşÔBkR_ĐO̟̚đźűüsĆźĺĚyčăÉŔułęĢé
iBeF˝Ź19N520úA˝Ź21N25új